こんにちは!最近知り合いが出産したむーむーさんです。
出産祝いとして、様々なプレゼントをお贈りすると思います。そんな時に、わからないことや、疑問がいっぱいありませんか?
「いつ贈ったらいいのだろう」「タイミングは?」「いくらくらい?相場は?」
今回は、気を付けたいマナーや相場をご紹介します。ポイントがいっぱいありますので、ぜひ参考にしてくださいね。
出産祝いとは?

出産祝いとは
・赤ちゃんの誕生自体を祝う
・赤ちゃんの健やかな健康を祈る
・出産を無事に終えたお母さんへの祝い
・新しい命を迎えた家族へのお祝い
これらの意味合いがあります。
出産や育児に関しては、昔からしきたりや行事が色々あり、各地によって様々なものがあります。
昔から出産は、女性の大役とされ、経験する難事の一つとされております。そのため、無事に妊娠から出産、育児にわたるまで、神様(産神様)にお供え物をして、安産や赤ちゃんの健康に成長することを祈願したと言われております。
このことから、無事に出産が終わると、神様に供え物をして、感謝を伝え、これからも母子ともに健やかであることをお祈りしたわけです。これが現代の出産祝いに繋がり、母子の健康と成長をお祝いする行事になったというわけです。
嬉しい行事なので、大切にしたいものです。
出産祝いを贈るタイミング

目安は「退院1週間~1か月後」
無事に退院した母子が落ち着いたころを見計らって出産祝いをお贈りします。
私の経験でもそうですが、産婦さんが退院するのは問題がなければ大体1週間~10日くらいです。入院中には、出産した後の子育てに関する試練が待っています。体調が優れない中、子育てのやり方を学びながら病院生活を送っております。なかなか大変なものです。
ここで出産祝いをお贈りする時に重要なのは、
出産を終えた産婦さんを気遣う気持ちです。
親しい間柄では、産院に直接お祝いに伺ったりすることも多くありますが、産後すぐのお母さんは落ち着かず、大変なものです。少し挨拶して、言葉を交わすくらいで早めに失礼することが気遣いです。お化粧や身なりを整えることができないので、お母さんにとっては嫌だと感じる人も多くいらっしゃいます。
産婦さんが気疲れしないように、配慮してあげることが重要ですね。
なお、お七夜と呼ばれる習慣もあります。
お七夜(おしちや)とは誕生から7日目の夜に赤ちゃんの健やかな成長を願って行うお祝いである。平安時代からつづく民俗行事で、生まれた子に名前をつけて、社会の一員として仲間になることを認めてもらう儀式である。
出典:Wikipediaより
産婦の体調の回復と赤ちゃんの無事を願って、産後7日目の夜にお祝いをしたのです。1週間は落ち着かないため、お祝いを控えるという習わしですね。
自宅に贈るという手段

お祝いは種類も豊富です。
手土産程度に持っていけるものから、おむつケーキの様に、サイズの大きなものまであります。
病院によっては、直接持っていくのは不向きの場合もあります。
車を持っていて、行き来が楽な場合には持参でも可能でしょうが、基本的には荷物になる物は控えた方が無難でしょう。
そこで、
退院のタイミングを見計らって、産後の2.3週間後くらいに自宅にお贈りする方法もよいでしょう。
配達であれば、負担も少なく、喜んで受け取ってもらえると思いますよ。
いつまでに贈ればよいか
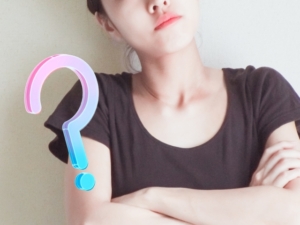
お祝いなのでいつでもいいのではないかと思いがちですが、そうでもありません。
出産祝いをもらった方には、内祝いという出産祝いのお返しを行います。
それが、産後1か月後。
お宮参りの時期に合わせて産後1か月後から赤ちゃんの名前をお知らせする意味で内祝いをお返しをします。
そのため、出産祝いをもらうのが遅すぎると、内祝いの準備が大変になってしまいます。お返しの準備は出産祝いをもらった方に、まとめて準備するのが一般的です。一緒に準備できないとなると、とっても手間がかかりませんか?遅くても1か月以内にお贈りするのが相手にとってもよいでしょう。
出産祝いの相場は?

出産祝いは、贈る人との関係によって変化します。
・兄や姉:10,000~30,000円・弟や妹:10,000~30,000円
・伯父叔母などの親族:10,000~20,000円
・いとこ:10,000~20,000円
・甥・姪:5,000~10,000円
・会社関係(上司・先輩):3,000~10,000円
・友人:3,000~10,000円
それぞれの関係性によって金額が変わります。
もちろん、私の様に、以前にお祝いを貰ったことがある人であれば、同等の金額でお贈りするのが良いでしょう。
まとめ
出産祝いをお贈りするのは
産後1週間~遅くても1か月以内にお贈りしましょう。
病院に持ち込むのではなく、ママさんが退院した後に配達でお贈りするのがお勧めです。
出産を終えた産婦さんは、とても大変です。できる限り相手を気遣ったお祝いとなれることを祈っております。